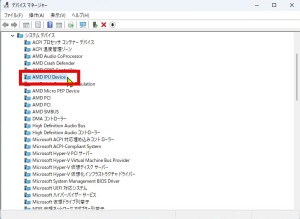AMD Ryzen AI はEdge AIを実現するための技術です。
対応するチップセットは当然AMD製のもので、その中でもCPU, GPUと合わせてNPUが載っているものです。
NPUを使うと、ローカルのデバイスで、かつ少ない電力消費で高速にAIが実現できるというもの。
楽しそうなんですが、PCの初期状態だとRyzen AI Softwareはインストールされていないはずです。
そこで本稿では Ryzen AI Softwareのインストール手順 を紹介します。
インストール手順は 公式ページ にきちんとまとめられていて、あまり悩むところはないと思っています。
ただネットを見ると、ちょっと苦労したという情報が見つかります。
そこで補足情報を含めてAMD Ryzen AI Softrwareのインストール手順を見ていくことにします。
これまでにローカルPCに自分で機械学習・深層学習用の環境を作ったことがあれば難しくないと思います。それに対してこのあたりの経験がないと理解しづらいところもあるかもしれません。
それでも手順通りにやればインストールできるはず。
本稿は長めの記事です。続きを読む
全部を一気にやらなくても問題ありません。項目ごとに頭から順番に進めてください。